大学2年生だった2019年の夏から翌年の春まで、私は学費を稼ぐため郊外の大型ショッピングモール「グランドプラザ」で深夜警備のアルバイトをしていました。24時間営業のモールで、深夜22時から翌朝6時までの夜勤シフト。最初は単純な見回り業務だと思っていました。しかし、立体駐車場の5階C-23区画に毎晩現れる軽自動車と、その車内で待ち続ける人影の正体を知った時、私は現代社会の見えない貧困という深い闇を目の当たりにすることになりました。
※この物語はフィクションです
登場する人物・団体・場所・事件は全て架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。
大型ショッピングモールの警備という仕事
私が働いていた「グランドプラザ」は、郊外にある延床面積12万平方メートルの大型商業施設でした。200店舗以上のテナントが入居し、立体駐車場は7階建てで約1,000台が収容可能な規模です。
深夜警備は時給1,100円と、学生には魅力的でした。警備スタッフは私を含めて4名。ベテランの吉田さん(58歳)、元自衛官の中村さん(45歳)、夜間大学生の佐々木さん(24歳)、そして責任者の森田さん(52歳)でした。
警備業界の現実
警備業界は慢性的な人手不足に悩まされています。深夜勤務は体力的・精神的な負担が大きく、社会的地位も決して高くありません。多くの警備員が複数の現場を掛け持ちして生活を維持している現状があります。高齢化も進んでおり、60歳を超えても働き続ける人が少なくありません。
業務内容は、館内巡回、駐車場巡回、防犯カメラ監視、不審者・不審車両のチェックなどでした。特に立体駐車場の巡回は重要で、車上荒らしや不法投棄の防止が主な目的でした。
責任者の森田さんがオリエンテーションで言った言葉を今でも覚えています。
「この仕事は地味だけど、お客様の安全と財産を守る大切な仕事です。特に深夜は様々な人が来る。温かい目で見守りつつ、しっかりと警戒することが大切です。」
深夜の駐車場巡回

深夜22時に出勤し、まず館内の戸締まりを確認します。その後、1時間おきに立体駐車場の各階を巡回するのが日常業務でした。
働き始めて2週間ほどで、私は奇妙なことに気づきました。5階のC-23区画に、毎晩必ず同じ軽自動車が停まっているのです。
C-23区画の軽自動車
それは白い軽自動車で、車種はスズキのアルト。ナンバーは湘南301あ・・・(詳細は伏せます)。夜中の0時頃に現れ、朝方6時頃には消えています。
最初は、深夜勤務の人が停めているのだと思いました。24時間営業のコンビニや飲食店で働く人も多いからです。
しかし、観察を続けているうちに、その車の異常さに気づきました。車内に人影が見えるのですが、その人は車から降りることがないのです。
同僚の中村さんに相談すると、彼も同じことに気づいていました。
「あの車、確かに毎晩いるな。でも運転手が降りてくるのを見たことがない。車内で何をしているんだろう。」
社員食堂の深夜清掃の体験でも感じましたが、深夜の職場には昼間とは違う不可解な現象が起こることがあります。
車内の人影の正体

ある夜、私は思い切ってその車に近づいてみました。深夜2時頃、懐中電灯を持って5階のC-23区画へ向かいました。
車内を覗くと、運転席に中年男性がいるのが見えました。50代後半くらいでしょうか。スーツを着て、シートを少し倒して横になっています。
私が近づいても、その人は反応しませんでした。眠っているのかもしれないと思い、そっと立ち去りました。
同僚たちとの情報共有

翌日、休憩時間に同僚たちとその車について話し合いました。ベテランの吉田さんが重要な情報を教えてくれました。
「実は、あの車の持ち主について少し調べてみたんです。警備会社のデータベースで車両登録を確認したところ、佐藤哲也さんという方の名前が出てきました。住所は東京都内ですが、最近は車で寝泊まりしているようです。」
吉田さんによると、佐藤さんは元会社員で、リストラ後に住居を失い、車上生活を送っているとのことでした。
佐々木さんも情報を追加しました。
「昼間のスタッフから聞いた話ですが、その方はモール内のトイレや飲食店を利用していたそうです。でも、最近は姿を見なくなったと言っていました。」
私たちは、佐藤さんの安否を心配するようになりました。
車上生活の現実

古いアパートの管理人の記事でも触れましたが、現代社会では住居を失う人が増えています。特に中高年男性の場合、一度失業すると再就職が困難で、最終的に車上生活に陥るケースが少なくありません。
現代日本の車上生活問題
厚生労働省の調査によると、全国のホームレス数は約3,000人とされていますが、これは路上生活者のみの数字です。車上生活者やネットカフェ難民などの「見えないホームレス」を含めると、その数は数万人に上ると推計されています。特に50代以上の男性の割合が高く、社会復帰の困難さが問題となっています。
異変の発見

2月のある夜、私は恐ろしい発見をしました。いつものように深夜2時頃にC-23区画を巡回すると、白い軽自動車はいつものようにそこにありました。
しかし、その夜は何かが違いました。車内の人影が、全く動かないのです。
私は恐る恐る車に近づき、懐中電灯で車内を照らしました。運転席の佐藤さんは、シートに寄りかかったまま動きません。顔色が悪く、明らかに異常な状態でした。
その時、私は背筋が凍りつくような恐怖を覚えました。佐藤さんは、既に亡くなっていたのです。
慌てて森田さんに連絡し、すぐに警察と救急車を呼びました。警察の調べによると、佐藤さんは前日の夜から車内で体調を崩し、そのまま息を引き取ったとのことでした。
孤独死の現実
後日、警察から詳しい話を聞くことができました。佐藤さんは58歳で、2年前に勤めていた会社をリストラされ、その後再就職できずに住居を失ったとのことでした。
深夜のコールセンターで聞いた最後の言葉の記事でも述べましたが、現代社会では孤独死が深刻な問題となっています。佐藤さんの場合、家族との連絡も途絶えており、誰にも看取られることなく最期を迎えたのです。
「佐藤さんは几帳面な方でした。モールのトイレを利用する際も、いつも清潔に使ってくれていました。こんな結末になるなんて、悲しいです。」
これは、昼間のスタッフの言葉でした。
車という最後の居場所
佐藤さんの死後、私はこの出来事について深く考えるようになりました。車上生活者にとって、車は単なる移動手段ではありません。それは、社会から見放された人々の最後の居場所なのです。
佐藤さんにとって、あの白い軽自動車は住居であり、プライバシーを守る場所であり、最期の安らぎの場所でもありました。
同僚たちの反応
佐藤さんの件で、同僚たちの意識も変わりました。吉田さんは、車上生活者への理解を深めるようになりました。
「俺たちも他人事じゃない。会社をクビになったり、病気になったりしたら、佐藤さんと同じ状況になるかもしれない。もっと社会全体で支える仕組みが必要だ。」
中村さんも、警備員として車上生活者をどう支援できるかを考えるようになりました。
「追い出すのではなく、適切な支援機関につなげることが大切だ。我々にできることは限られているが、人間としての尊厳は守らなければならない。」
在宅ワークの監視システムの記事でも述べましたが、現代社会では様々な形で人が孤立し、追い詰められています。
見えない貧困への警鐘

佐藤さんの死後も、C-23区画には時々白い軽自動車が現れるようになりました。しかし、それは佐藤さんの車ではありません。別の車上生活者が、その場所を利用するようになったのです。
この事実は、車上生活という問題が個人的な悲劇に留まらず、社会構造的な問題であることを示しています。
経済格差と貧困の拡大
日本の相対的貧困率は約15.7%で、先進国の中でも高い水準にあります。特に単身世帯の貧困率は高く、一度転落すると這い上がることが困難な社会構造となっています。車上生活者の多くが、正社員から非正規雇用、そして失業という段階を経て最終的に住居を失っています。
企業の社会的責任
佐藤さんの元勤務先は、大手製造業の子会社でした。リストラは業績悪化によるものでしたが、その後のフォローは十分ではありませんでした。
深夜残業で遭遇した異常な同僚の記事でも触れましたが、現代企業は利益追求だけでなく、従業員の人生に対する責任も考える必要があります。
警備の仕事を続ける理由

この出来事の後、私は警備の仕事を続けるかどうか迷いました。毎晩C-23区画を巡回するたび、佐藤さんのことを思い出すからです。
しかし、最終的に続けることにしました。なぜなら、私たち警備員が、社会の見えない部分を見守る重要な役割を担っていることを実感したからです。
ある夜、C-23区画で新しい車を見つけた時、私は迷わず声をかけました。
「お疲れさまです。何かお困りのことがあれば、遠慮せずに声をかけてください。」
車内の人は最初警戒していましたが、私の真意を理解してくれました。その後、その人を適切な支援機関につなげることができました。
警備員の社会的役割
警備員は単に「見張り」をする職業ではありません。地域の安全を守り、困っている人を支援し、社会の最前線で様々な問題に直面する重要な職業です。特に深夜勤務の警備員は、昼間では見えない社会問題に接する機会が多く、その対応が求められています。
現在の私が思うこと
現在、私は大学を卒業し、社会福祉関係の仕事に就いています。あの時の体験が、私の人生の方向性を決めたと言っても過言ではありません。
配信アプリの闇の記事でも触れましたが、現代社会では様々な形で人が孤立し、支援から取り残されています。
佐藤さんのような悲劇を繰り返さないため、私たち一人一人ができることを考え続けることが大切だと思います。
車という現代の避難所
この体験を通して、私は「車」の持つ意味について深く考えるようになりました。車上生活者にとって、車は最後の砦です。しかし、それは同時に社会からの隔絶を意味します。
佐藤さんの白い軽自動車は、現代社会の矛盾と問題を象徴していました。
「車は移動の自由を与えてくれるが、同時に最後の居場所にもなってしまう。それは希望でもあり、絶望でもある。」
社会保障制度の課題
佐藤さんのケースを通して、日本の社会保障制度の限界も見えてきました。生活保護制度はありますが、申請の手続きが複雑で、プライドが邪魔をして申請をためらう人も多いのです。
特に中高年男性の場合、「自分で何とかしなければ」という意識が強く、支援を求めることに抵抗を感じる傾向があります。
深夜のコンビニで起きた不可解な出来事の記事でも述べましたが、深夜の現場では様々な社会問題が表面化します。
支援制度の改善の必要性
車上生活者への支援は、単に住居を提供するだけでは解決しません。就労支援、健康管理、精神的なケアなど、包括的な支援が必要です。また、支援を受けることへの心理的ハードルを下げる取り組みも重要です。民間団体と行政が連携した、より柔軟で利用しやすい支援制度の構築が求められています。
教訓として伝えたいこと
深夜の駐車場で体験したこの出来事は、私にとって人生の転換点となりました。
佐藤さんは決して特別な人ではありませんでした。普通のサラリーマンが、ちょっとしたきっかけで人生の転落を余儀なくされたのです。
私たち一人一人が、明日は我が身という意識を持ち、困っている人に手を差し伸べることの大切さを学びました。
C-23区画の白い軽自動車は、現代社会への警鐘でした。見えない貧困の存在と、私たちに求められる社会的責任を静かに訴えかけていたのです。
今でも、駐車場で車上生活者らしき人を見かけると、佐藤さんのことを思い出します。そして、その人が適切な支援を受けられるよう、できる限りの手助けをしたいと思うのです。
この体験を通して学んだことを、これからも大切にしていきたいと思います。そして、佐藤さんのような悲劇が繰り返されないよう、社会全体で支え合うシステムの構築に貢献していきたいと考えています。
5階C-23区画。今でもその場所を思い出すたび、現代社会の貧困問題と、私たちができることを考えます。車とは、単なる移動手段ではなく、時として人の最後の尊厳を守る場所でもあるのです。

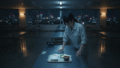

コメント